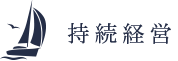5.経営者への提案について
まず、最初に面談を行う場合、経営者に対して報告を求められるケースがほとんどです。
一方、面談者に対しては守秘義務があり、経営者に対してストレートに報告することは難しいです。
また、その報告時は、経営者に対して提案する機会ともなり得ます。
さらに、経営者自身が面談を体験している場合と、そうでない場合とで、報告や提案の内容も留意した方が良い点があります。
ここでは、以下の3点について説明いたします。
①経営者への報告内容
②経営者への提案時の留意点
③最初のニーズからの展開に関する提案
①経営者に対する報告内容
・報告に当たっては、面談者に対しては守秘義務があり、経営者に対して面談者から聞いた内容を報告することは出来ない旨を冒頭説明します。
この守秘義務を守らないと、私が聞いた内容が第3者に伝わっているのを本人が知ると、その後の面談では本音を話さなくなってしまうからです。
・個別の内容に触れずに報告できる一つの方法は、拠点別や部門別に平均面談時間をグラフにして見せることです。
1回の面談時間は、標準で1時間半を想定しています。
しかし、1回に行うテーマ(「価値観」「夢」など)に必要な時間は、30~60分です。人によって変化しますが、最大でも1時間以内です。
一方、毎回面談の冒頭に、「スッキリしないこと」や「モヤモヤしていること」を、必ず面談者に聞いています。
この面談者の悩みは、人によって、また時期によって、全く違ってきます。
悩みを話す時間が、ほとんど無い(0分)場合もあれば、1時間以上の場合もあります。
つまり、同じ回数の面談を行っても、個人別にその平均面談時間は異なってきます。
そして、それを更に、拠点別や部門別にその違いを見てみると、ストレスを抱えている拠点や部門が、相対的に浮かび上がってきます。
・さらに、個別に報告を求めてくる経営者の方も、いらっしゃいます。
この場合、有効な一つの方法があります。
それは、各自の「価値観」を、本人の同意のもとに公表する方法です。
そもそも「価値観」は、本人が「大切にしているもの」であり、生まれ持った性格と過去の人生で選んで来たものが加味されて、その人の「個性」を形成しています。
その本人の「価値観」に他人から踏み込まれると本人は苛立ちますが、「価値観」に沿っている期間は満足度が高い状態が維持されます。
一方「価値観」は人によって全く異なり、お互いがお互いの「価値観」を尊重することが、チームワークの基本になると考えられます。
通常は、自分の価値観に気づいた後に、相手の価値観を想像するのですが、自分の「価値観」を公表することで、同時に他人の「価値観」を知ることも可能になります。
本人が自分の「価値観」を公表することに同意することで、他人の「価値観」を知ると同時に、経営者もそれらを知ることが可能になります。
他人にも、経営者にも、「自分の価値観」が知られたとしても、マイナスになることが全く無いと思われます。
もちろん、本人が同意しない場合は非公開となりますが、他人の「価値観」も分かりません。必要に応じてその人の「価値観」を想像しなければなりません。
・そして、個別に報告を求めてくる経営者の方に、別の方法で実施した例があります。
それは、私が面談を通じて感じたその人の「人となり」を、本人の同意のもとに公表する方法です。
最終面談時に、私が感じたその人の「人となり」を本人に説明して、その表現で良いかどうかを確認します。
修正を求められれば、その修正通りの内容を、経営者には報告しました。
つまり、面談における守秘義務は果たしていることになります。
②経営者への提案時の留意点
経営者への報告時は、提案する絶好の機会ともなり得ます。
②-1.経営者自身が面談を体験している場合
・面談冒頭に経営者の「スッキリしないこと」や「モヤモヤしていること」など、経営者の悩みを傾聴するようにしています。
その際、経営者の悩みが、特定の従業員に関する場合があります。
その時、私がその特定の従業員との面談時に感じた内容を報告することがあります。
この場合、留意していることは、守秘義務に違反しないように、出来るだけ「結論」を先に述べるようにしています。
その「結論」を補完する内容は、概略的な内容に限って話すよう注意しています。
・具体的な悩みが、特定の従業員や後継者に関することであれば、次回の面談までに1枚の用紙に「特定者向けの面談概要とスケジュール」をまとめて提案します。
また、当方から具体的な提案を行う時には、二つの提案を図表や1枚に用紙にまとめて、どれから進めるかを確認していきます。
経営者の興味や優先度により、提案内容の進め方を決めるように、留意しています。
②-2.経営者自身が面談を体験していない場合
・経営者への報告する時にしか、提案する機会はありません。
当然、報告することが、第1目的となります。
従って、報告後に提案することは、非常に絞ったテーマとし、限られた時間での提案となります。
また、その提案内容も1枚の用紙にまとめて、図表を混ぜることにも留意しています。
③最初のニーズからの展開に関する提案
・最初のニーズとは、「従業員のモチベーションアップ(やる気)」と「新人の離職防止」を意味します。
最初のニーズからの展開やニーズの例は、以前記載した通りです。
1)「リーダー・管理職のモチベーションアップ」のニーズへの展開
2)「社長自身」への展開
3)「後継者」への展開
4)「グループ内のチームワークを向上させたい」というニーズ
5)「グループ内での特定の問題社員の意識を向上させたい」というニーズ
6)「グループ内でのリーダー・管理職によるパワーハラスメントを無くしたい」とうニーズ
・ところで、持続経営では、「100年企業」を目指せるように支援したいと考えています。
100年企業とは、3世代以上に渡って会社が潰れない状態の企業だと認識しています。
100年という期間では、人材が一番重要と考えております。
特に、2)「社長自身」への展開 や 3)「後継者」への展開 の人材支援は重要と認識しています。
ただし、最初のアプローチは、「従業員」や「新人」からであっても、順次展開して行ければ良いと考えております。
・また、人材支援以外でも、必要に応じて展開していきたいと考えています。
1)「管理会計」導入のメリットの認識
2)「会社の強み」と「事業領域」についての自覚
3)「事業承継」についての社長の考え方
4)「自社株」比率についての認識
特に、2)「会社の強み」と「事業領域」についての自覚 は重要と認識しています。